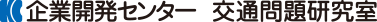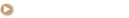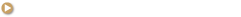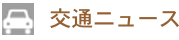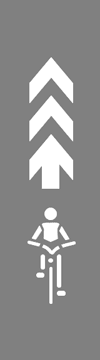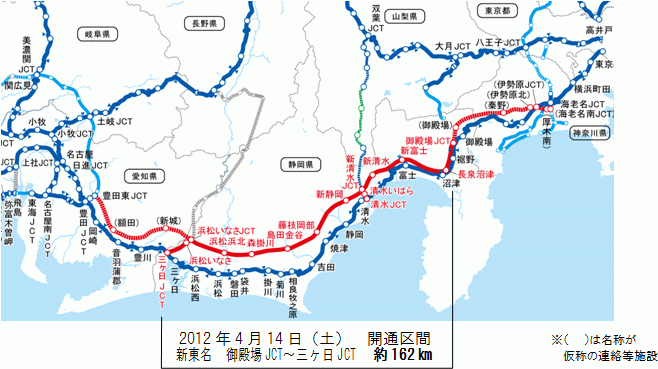2012.12.20 |
■後部座席のシートベルト、いまだ低水準
――警察庁、JAF
警察庁とJAFは、このほど「シートベルト着用状況全国調査」の結果を発表しました。
それによると、一般道での着用率は、運転席が97.7%、助手席が93.2%、後部座席が33.2%となりました。
また、高速道路ではそれぞれ、99.5%(運転席)、97.7%(助手席)、65.4%(後部座席)となり、一般道、高速道路ともに例年同様、後部座席の着用率の低さが目立つ結果となりました。
同庁では、タクシー乗り場、行楽地、高速道路のSA・PA等、後部座席を利用する者や家族連れが多い場所での交通安全教育、後方啓発活動に力を入れていく方針です。
詳細は警察庁のHPまで
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/seatbelt/npa_jaf_research24.pdf |
|
2012.11.09 |
■新しい『エコドライブ10のすすめ』を策定
――エコドライブ普及連絡会
警察庁はじめ、関係省庁で構成するエコドライブ普及連絡会では、このほど「エコドライブ10のすすめ」の内容の見直しを行い、新たな「エコドライブ10のすすめ」を策定しました。
新しい「エコドライブ10のすすめ」は次の通りです。
①ふんわりアクセル「eスタート」
②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転
③減速時は早めにアクセルを離そう
④エアコンの使用は適切に
⑤ムダなアイドリングはやめよう
⑥渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備
⑧不要な荷物はおろそう
⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう
⑩自分の燃費を把握しよう
詳細は環境省のHPまで
http://www.env.go.jp/air/info/ecodrive_m/ |
|
2012.10.19 |
■自転車を取り巻く現状が明らかに
――警察庁
警察庁は、このほど「自転車の交通ルールの徹底方策に関する懇談会」の初会合を開きました。会合では、自転車の交通事故の実態と交通ルールの徹底方策について現状の説明が行われました。
それによると、自転車の交通事故は、全交通事故の2割を占め増加傾向にあること、自転車対歩行者の交通事故は、10年間で約1.5倍に増加していることなど、自転車を取り巻く環境が憂慮すべき状況にあることなどが紹介されました。
また、アンケート調査から「車道通行が原則であり、歩道通行は例外」というルールは知っているものの、「あまり守らない」「守らないことがある」と回答した者が過半数を占めたほか、歩道を通行できる場合を正しく知らない人が38%に上るなど、通行ルールの遵守・浸透が不十分であるという現状の報告等が行われました。
同庁では、今後の会合でさらに議論を重ね、年内に提言をまとめる方針です。
詳細は警察庁HPまで
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kondankai/siryo1-2.pdf |
|
2012.09.10 |
■チャイルドシートの肩ベルトの調整を呼びかけ
――国土交通省
国土交通省では、子どもの体がチャイルドシートの外に出て、チャイルドシートの肩ベルトが首にかかり負傷するという事故が発生したことから、チャイルドシートの肩ベルトを正しく調整することを呼びかけています。
チャイルドシートの肩ベルトによる子供の負傷防止のために以下の項目を徹底してください。
①肩ベルトがお子様の身体にフィットしているかきちんと確認しましょう。
*肩ベルトの高さは、子どもの成長に合わせて調整する。
*子どもを乗せる度に、必ず肩ベルトの緩みを取り、子どもの身体にフィットするように肩ベルトの長さを調整する。
*詳しい調整方法は、それぞれのチャイルドシートの取扱説明書で再度確認する。
②小さなお子様を車内に一人にするのは危険なので、くれぐれも、子ども車内に放置しない。
詳細は国土交通省HPまで
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_001152.html |
|
2012.08.16 |
走車と遭遇した際の事故防止ポイントを紹介した動画を公開 ■走車と遭遇した際の事故防止ポイントを紹介した動画を公開
――JAF
JAFは、高速道路上で逆走車による事故が毎年発生していることから、ホームページのJAFチャンネルに、逆走車と遭遇した際の事故回避のポイントなどを解説した動画を公開しました。
警察庁の調べでは、過去5年間で高速道路における逆走事故は106件発生しており、そのうち20件が死亡事故と多発しているのが現状です。
JAFはNEXCO中日本の協力を得て、開通前の高速道路で逆走車に遭遇した際の状況を再現し収録。過去の事故事例から、逆走事故が起きやすい場所や原因を解説するとともに、サービスエリアなどに設置されている逆走防止装置などの防止策を紹介してドライバーに注意を呼び掛けています。
動画は以下のアドレスから視聴できます。
JAFが再現 逆走車の恐怖
http://ch.jafevent.jp/detail.php?id=182_0_85917 |
|
2012.07.18 |
高速道路の渋滞のピーク、8月11日~15日にかけて ■高速道路の渋滞のピーク、8月11日~15日にかけて
――財団法人道路交通情報センター
財団法人日本道路交通情報センターは、夏季期間中の渋滞予測を発表しました。 それによると、高速道路では郊外へ向かう下り線が8月11日(土)~12日(日)に、郊外から戻る上り線は8月14日(火)~15日(水)に渋滞が多く発生すると予測しています。
また、もっとも混雑が予測される路線は関越自動車道の花園IC(12日・下り線)、高坂SA付近(14、15日・上り線)でピーク時の渋滞の長さを45㎞としています。
同センターでは、電話やインターネット等で最新の道路交通情報を確認のうえ、ゆとりをもって出かけることを呼びかけています。
詳細は日本道路交通情報センターHPへ
http://www.jartic.or.jp/guide/yosoku.html |
|
2012.06.19 |
|
|
|
2012.06.06 |
超小型モビリティー、電気バス導入等のガイドラインを公表 ■超小型モビリティー、電気バス導入等のガイドラインを公表
――国土交通省
国土交通省は超小型モビリティの導入、電気バスの導入および充電施設のガイドラインを公表しました。
超小型モビリティは、自動車よりもコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れた1~2人乗り程度の車両で、人口減少・高齢化時代に対応した街づくりに適した交通手段として期待されています。
今回発表されたガイドラインでは、超小型モビリティの定義、導入意義、活用が想定される場面の明確化、車両仕様に対するニーズ等が示されました。また、電気バスについても車両の特徴を踏まえた導入計画に関する考え方が紹介されています。この他、充電施設に関しても設置のガイドラインがまとめられました。
同省では今回の発表したガイドラインを活用し、地域への導入および利用環境の整備、自動車メーカー等への開発・実用化、規格・基準の具体化等について検討を進めていく方針です。
詳細は国土交通省HPまで
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000006.html |
|
2012.05.15 |
■高速ツアーバスの安全確保に向け新制度への移行促進
――国土交通省
国土交通省では、関越自動車道で発生した高速ツアーバスの死傷事故を受け、新たな高速乗合バス制度への移行時期を当初予定していた平成25年度末から前倒しする方針を固めました。
同省では、平成25年度末までに、高速ツアーバスを運行している旅行業者にバス事業の許可を取得させ、道路運送法に基づく安全確保の責任を負わせるとともに、運行を委託する貸切バス事業者にも安全確保措置を確実に実施させる新制度の移行を目指してしましたが、今回の事故を踏まえ、高速ツアーバス事業者の新制度移行準備を加速させ、新制度の早期移行を促進させるとしています。
詳細は国土交通省HPまで
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000082.html |
|
2012.05.09 |
■高タイヤ、約4割が整備不良!
――日本自動車タイヤ協会
日本自動車タイヤ協会では、4月5日~8日にかけて、全国7ヵ所でタイヤの点検を実施し、その結果を発表しました。
乗用車270台、貨物車19台の計289台にタイヤ点検を行った結果、約4割強の119台にタイヤの整備不良がみられました。もっとも多かったのは「空気圧不適正」で、乗用車(93台)、貨物(7台)と、ともに3割強の車にタイヤの空気圧の不具合がみられました。
同協会では、この結果を踏まえ、正しい空気圧管理が安全走行やエコドライブの基本であることなどを啓発していくこととしています。
詳しくは日本自動車タイヤ協会のHPまで。
http://www.jatma.or.jp/news_psd/news1165.pdf |
|
2012.04.26 |
■ロードサービス依頼内容、過放電バッテリーが第1位
――JAF
一般社団法人日本自動車連盟(以下JAF)によると、平成23年度に出動したロードサービス救援件数は258万2,773件と、ほぼ前年並みでした。
救援依頼内容では「過放電バッテリー」が88万2,791件でもっとも多くなりました。また、前年に比べて増加したものは「タイヤのパンク」「落輪」「破損バッテリー」「スタータモータ」でした。
JAFでは、トラブルの原因となるタイヤの空気圧不適切やバッテリーの劣化等については、確実に点検・整備を行っておくことで防げることから、定期的な車両点検の実施を呼びかけるとしています。
詳しくはJAFのHPまで
http://www.jaf.or.jp/profile/news/file/2012_03.htm |
|
2012.04.16 |
■飲酒運転撲滅へ~全国初罰則付条例9月21日施行~
――福岡県
福岡県では、全国初の罰則付き飲酒運転撲滅条例の一部を4月1日から施行していますが、準備期間を設けていた罰則条項についても9月21日から施行されます。その主な内容は次の通りです。
飲酒運転で検挙された場合
・違反者はアルコール依存症検査の受診に努めなければなりません。
・一定期間内に再度違反した場合、同診断の受診が義務付けられます。→受診しない場合は5万円以下の過料となります。
飲酒運転違反者に酒類を提供した飲食店は、
・公安委員会から飲酒運転防止措置への取組みを指示されたにもかかわらずその取組を怠った場合、店名の公表と併せて公安委員会の指示書の店内掲示が義務付けられます。→指示書を掲示しない場合は5万円以下の過料となります。
通勤・通学中に飲酒運転で検挙された場合は、
・公安委員会から勤務・通学先に通知されます。
・通知を受けた事業者は、違反者が再び飲酒運転をしないよう対策を講じなければなりません。
*詳しくは福岡県HPまで
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a03/insyuuntenbokumetsu-jourei.html |
|
2012.03.29 |
■ 路上故障のトップは電気装置 高速道路では走行装置
――国土交通省・JAF
国土交通省は、JAFの協力のもと、平成23年9月~11月に発生した一般道・高速道路における自動車の路上故障の調査を行いました。調査結果によると、路上故障の発生件数は13万9,167件で、前年(22年9月~11月)より1万7,543件増加しました。
装置別の故障発生件数がもっとも多かったのは「電気装置」の6万7,190件(全体の48.3%)、次いで「走行装置」(同26.0%)、「エンジン本体」(同6.5%)と続きました。一般道路でもっとも多かった故障は「電気装置」(同52.8%)であったのに対し、高速道路は「走行装置」(同51.9%)がもっとも多く、一般道路と高速道路で路上故障の発生状況に違いがみられました。
また、部位別の故障発生率を道路別にみると、一般道路では「バッテリー」故障が最多で42.1%を占め、なかでも「過放電」が「バッテリー」故障全体の8割超に達しています。一方、高速道路では「タイヤ」故障が最多で51.2%(前年比10.3ポイント増)にのぼりました。
同省では、高速道路走行前に、タイヤの摩耗や外観の傷、空気圧の確認など日常点検を確実に実施することが故障防止につながるとしています。 |
|
2012.03.21 |
■衝突被害軽減ブレーキ 貨物自動車に義務づけへ
――国土交通省
国土交通省は、貨物自動車に衝突被害軽減ブレーキの装着を義務づけることを発表しました。同装置は、常にレーダーを発信して前方の車両等を捉え、停止車両に接近した場合にアラームを鳴らしてドライバーに注意を促したり、追突する危険が高まった際にブレーキを作動させたりします。
貨物自動車の事故に占める追突事故の割合が高く、乗用車と比べて死亡事故率が高いことから、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を一部改正し、衝突被害軽減ブレーキの技術基準を導入します。
義務化の適用時期は、新型生産車については、車両総重量22t超の貨物車と同13t超の牽引車が平成26年11月以降、同20t超22t以下の貨物車が28年11月以降。継続生産車については、同22t超の貨物車が29年9月以降、同13t超の牽引車が30年9月以降、同20t超22t以下の貨物車が30年11月以降となっています。 |
|
2012.03.16 |
世界初 肩・腰ベルト取付け部が着脱可能なシートベルトを開発 ■ 世界初 肩・腰ベルト取付け部が着脱可能なシートベルトを開発
――タカタ㈱
シートベルトやエアバッグなど自動車用安全部品を製造するタカタは、子会社のタカタサービス㈱が、肩ベルト取付け部と腰ベルト取付け部が着脱できる世界初のシートベルトを開発したと発表しました。キャンピングカーなどの後部座席用として6月より販売を開始する予定です。
従来キャンピングカーの後部座席に取り付けられているシートベルトの大半は2点式腰ベルトタイプでしたが、7月に施行されるシートベルトの国内新技術基準において、後部座席のすべてで腰ベルトと肩ベルトが付いた3点式シートベルトの装備が義務づけらます。
今回開発したシートベルトは、国内新技術基準を満たしているほか、最大の特徴は取付け部が着脱式になっており、車のキーなどを使用して簡単に取り外せ、取付けもワンタッチでできる点にあります。とくに、座席を倒してフルフラットにし、ベッドなどとして使用する際には、取付け部を外すことで出っ張りが残らないため、快適性が向上します。
 |
|
2012.03.13 |
EVから電源を取る給電装置を発売へ 最大出力1500W ■ EVから電源を取る給電装置を発売へ 最大出力1500W
――三菱自動車工業㈱
三菱自動車工業は、同社の電気自動車(EV)「i-MiEV(アイ・ミーブ)」と「MINICAB-MiEV(ミニキャブ・ミーブ)」から大電力を出力することができる電源供給装置「MiEV power BOX(ミーブ パワーボックス)」を4月27日に発売します。
同装置は、車体の急速充電コネクターに接続することで、大容量の駆動用バッテリーに蓄えられた電力の一部を交流(AC)100Vで最大1500Wまで取り出すことができます。満充電された駆動用バッテリー(16.0kwh)に接続して1500Wで連続使用した場合、約5~6時間使用することができます。これは一般家庭の約1日分の電力消費量に相当します。
災害時の移動式電源車としての活用をはじめ、屋外イベントやキャンプなど幅広い用途での利用を想定しています。 |
|
2012.02.29 |
■自動車盗難の認知件数 8年ぶりに増加
――警察庁他
警察庁は、平成23年中の犯罪統計資料を公表しました。
そのなかで、自動車盗難の認知件数は、前年比4.8%増の2万4,927件で、15年以来8年ぶりに増加に転じました。このうち、「キーなし盗難」が約4分の3を占めています。
また、自動車盗難件数がもっとも多かった都道府県は、愛知県で5,026件にのぼりました。次いで、千葉県(3,247件)、茨城県(2,025件)、大阪府(2,000件)と続いています。
自動車の盗難を防止するためには、次に紹介するような対策を施すと効果的です。 *わずかな時間であっても、車から離れる際には、必ず窓を完全に閉め、キーを抜き、ドアをロックする。
*盗難防止装置のイモビライザーを装着する。車を購入する際には、標準装備か後付けできるかを確認し、可能であれば装着する。
*イモビライザー以外にも、バー式ハンドルロックやセンサー式警報装置、GPS追跡装置など、さまざまな盗難防止機器が販売されているため、状況に応じて効果的に活用する。
*月極駐車場は、夜間でも明るく防犯対策の整った場所を選ぶ。自宅の駐車場には、防犯灯や防犯カメラなどを備え付けると効果的。外出時は路上駐車をやめて、明るく監視の行き届いた駐車場を利用する。
*車内に財布やカバンなど貴重品を置きっ放しにしない。スペアキーや緊急用のカードキーをグローブボックス内に置いておくことも厳禁。 |
|
2012.02.20 |
聴覚障害者が運転できる車両 4月から二輪車なども可能に ■聴覚障害者が運転できる車両 4月から二輪車なども可能に
――警察庁
 警察庁は、聴覚障害者が運転できる車両について、これまで条件付きで認めていた普通乗用車に加え、二輪車やトラックなどにも拡大する方針を決めました。4月1日に道路交通法の施行規則を改正します。 警察庁は、聴覚障害者が運転できる車両について、これまで条件付きで認めていた普通乗用車に加え、二輪車やトラックなどにも拡大する方針を決めました。4月1日に道路交通法の施行規則を改正します。
平成20年6月の道路交通法施行規則改正により、聴覚障害者は、特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)の取付けと聴覚障害者標識(右図)の表示などを条件として、普通乗用車を運転することが認められました。
今回の法改正では、車種を普通貨物自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車に拡大します。なお、普通貨物自動車については、普通乗用車と同様に、特定後写鏡の取付けと聴覚障害者標識の表示を条件としています。 |
|
2012.02.14 |
■自転車ナビマークを設置 都内のモデル地区から順次
――警察庁
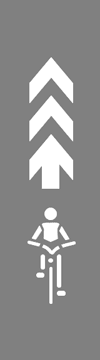
警視庁は、自転車が通る車道の左端にイラストつきで舗装を施した「自転車ナビマーク」(右図:アルファルト舗装上に設置したイメージ)の設置を始めました。
「自転車ナビマーク」は、自転車のイラストと進行方向を示す矢印を白色で描いたもので、自転車の走行路を明示し、歩道の歩行者との衝突や自転車の逆走防止を目的としています。
このほど、モデル地区の1つである東京都江戸川区の東京メトロ西葛西駅周辺に初めて設置されました。モデル地区はほかに、港区の品川駅港南口と小平市の小平駅南口があり、両地区にも順次設置し、設置効果の検証などを行います。
なお、「自転車ナビマーク」は法令に定めのない法定外表示であるため、表示自体に新たな交通方法を指定する意味はなく、通行方法は法令や道路標識等の交通規制に従うことになります。 |
|
2012.02.09 |
■新東名高速道路 4月14日に御殿場~三ヶ日が開通
――NEXCO中日本
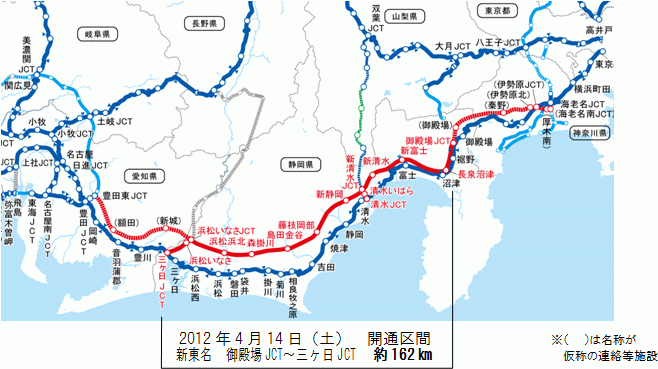
NEXCO中日本は、建設をすすめている新東名高速道路(以下、新東名)のうち、御殿場JCT(御殿場市)~三ヶ日JCT(浜松市)までの区間を、4月14日(土)15時に開通すると発表しました。開通する区間は約162kmにおよび、日本の高速道路で一度に開通する距離としては、これまででもっとも長くなります。
新東名は、東京と名古屋を結ぶ延長約330kmの高速道路で、今回、静岡県内を走る区間が開通します。開通によって現東名高速道路(以下、東名)と新東名に交通量が分散されることで、静岡県内で年間約2,500回発生している渋滞はほぼ解消される見通しです。
また、地震や異常気象などで東名か新東名のどちらかに交通規制がかかったり通行止めになった場合に、一般道などを使ってもう一方の高速道路へ移ることで、交通麻痺を回避することができます。
新東名の全線開通は、平成32年度の予定です。 |
|
2012.02.01 |
■最大1億円まで補償する自転車保険を販売開始
――au損害保険㈱
au損害保険は、賠償額を最大1億円まで補償する自転車保険「新自転車ワイドプラン」の販売を開始しました。
同プランでは、月払い410円(年払い4,500円)で対人・対物賠償額(個人賠償責任補償額)最大1億円、死亡・後遺障害400万円、入院一時金2万円、入院日額6,000円を補償する「イチおしコース」のほか、被害事故を受けた際の法律相談費用や弁護士費用なども補償する「イチおしプラスコース」など、補償内容に応じて3つのコースを用意しています。
なお、「新自転車ワイドプラン」の販売開始に伴い、補償額を最大5,000万円に設定していた自転車保険「自転車ワイドプラン」の販売は終了します。一方、月払い100円(年払い1,070円)で賠償額を最大1,000万円まで補償する「100円自転車プラン」の販売は継続します。 |
|
2012.01.19 |
■ハンドルに搭載可能なアルコール検知システムを開発
――㈱日立製作所・㈱日立エンジニアリング・アンド・サービス
日立製作所と日立エンジニアリング・アンド・サービスは、車のハンドル部分に取り付けることができる小型のアルコール検知システムを開発しました。
従来の装置は、呼気を吹きかける部分とアルコールを検知するセンサ部分が一体化しており、電源部などの周辺部分を含めると自動車へ搭載するには大きすぎるという問題がありました。
そこで今回、アルコール検知システム本体を小型化してダッシュボード内に収容できるようにしました。加えて、呼気の吹き込み口をハンドル部分に取り付けることにより、運転者が特別な動作を行うことなく運転時に近い姿勢を保ったまま息を吹きかけるだけで、呼気に含まれるアルコール濃度を厳密に測定することができるようになりました。
近年、飲酒運転根絶に向けた取組みが強化されており、昨年5月1日には、運送事業者が運転者に対して実施する点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することなどが義務化されています。 |
|
2012.01.10 |
居眠り運転警告装置「スリープバスター」2月より販売開始 ■ 居眠り運転警告装置「スリープバスター」2月より販売開始
――JUKI㈱
JUKIは、自動車の運転中に眠気の兆候を知らせ、居眠り運転を防止するシステム「Sleep Buster(スリープバスター)」を2月より発売すると発表しました。
「スリープバスター」は、㈱デルタツーリングが東京大学、大分大学、島根難病研究所などと共同研究をすすめ、内閣府が行う平成22年度産学官連携功労者表彰において、国土交通大臣賞を受賞した「居眠り運転警告シート」を商品化したものです。
この商品は、座席シートに装着したマットに内蔵されたセンサーで運転者の心拍・脈波などの生体信号をとらえ、運転者の状態を7段階で表示します。
そして、運転者が居眠り状態に入る前の「入眠予兆」を検知し、このまま運転を継続すると危険だと判断した際に、コントローラーの画面や音声で警告を出したり休憩を促す機能があり、居眠り運転による交通事故の未然防止の効果が期待されます。 |
|